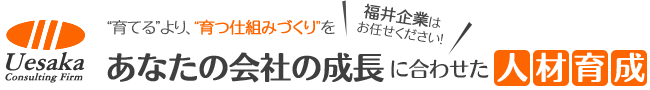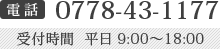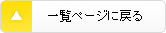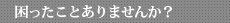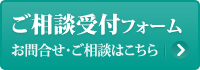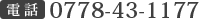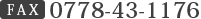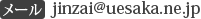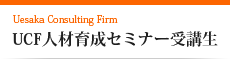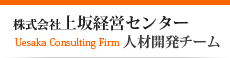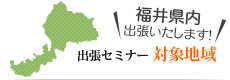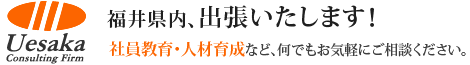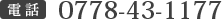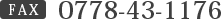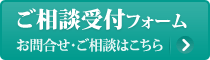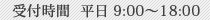「私の感覚では、育つ人って言うのは、勝手に芽がでてくる感覚なんですよ。
同じ環境でも、目立ってくるのが分かるんです。」
確かにそうですよね。これは、経営者であれば、誰もが持っている感覚だと思います。
では、「この芽が出てくる」スピードは、本人の資質に頼るしかないのか?
それにはいくつかの要素がからんでいると思います。
まずは、本人の資質は大きく影響します。
それには、知能や体躯、性格も作用しますが、それ以上に、生まれてから
入社までに経験してきた生活環境に大きく作用されると思います。
先天的なものと後天的なもの。
後天的なものについては、私はDPI(ダイヤモンド社製)を使って測定することが多いです。
それを“ふるいにかける”のが採用、ですよね。
従って、採用希望者をたくさん募ることができるかどうかが、
その企業の人材育成力を大きく左右する、というわけです。
ちなみに私どもは、少なくとも毎年採用人数の30倍以上の採用試験の受験者を集めることを目標としています。
次に、本人の資質は採用でふるった後、その選りすぐった種を撒く畠(はたけ)の土の質が問題となりますよね。
特に新卒を始めてから、この畠の土の質が一定レベルになるのに、
10年ぐらいはかかるのではないでしょうか。
その間は我慢です。肥料をたくさんあげたり、間引きしたりするしかない。
その肥料や間引きが、人材育成の環境づくりに相当するのではないかと思うのです。
最近、「仕組み」という言葉よりも「環境」という言葉の方がしっくりくるようになりました。
社内規律やルール、作業や業務のマニュアル・ガイドブック、
日報や週報、グループウェアなどのホウレンソウの仕組みづくりを「仕組み」と表現するなら、
「社風+仕組み=環境」 ではないかと。
仕組みはもちろんめちゃくちゃ大事なのですが、その仕組みづくり自体も、
環境を創っていくことで発展して行くものなのだと思います。
情報化が進み、色々な仕組みが可視化され、便利化されてきています。
しかし、その進化が進む一方で、人間自身のマインドが低下していっているのではないか、
もう少し言うと、やる気がないわけではないのだが、自分自身が忙しすぎて、
どうしてよいか分からず、結果的に、ルーチンワークに自ら埋没して、自己防衛を計る・・・。
そんな人、周りに居ませんか?
加えて、働き方も多様化し、一つの会社にとどまる期間は3年平均とか言われている社会状況。
これって、誰が悪いとかではなく、環境変化なのだと思うのです。
時の経過とともに、私たち日本人を取り巻く仕事環境が劇的に変化しているわけで、
経営者としてはこの変化を認めつつ、自社がその流れに流されないようにしていくしかない。
それを、弊社代表の上坂は今年、「Think Different」って表現したんだと思います。
環境づくりは土づくり。なので10年15年仕事になります。
外部からの刺激も大事なのですが、最も大事なのは経営者自身がそのことを大事にすること。
大事にするとは、すなわち 「企業の根底の価値観と位置付け、社内のあらゆることに関係させること」、
そして、手間暇をかけること、だと思います。
そういう意味では、農家の皆さんの取り組みを勉強すると良いかもしれません。
私も最近そのような本や冊子をよく読むようにしています。
我が社の土を、人がたくさん育つ“良い土”にしていきたいものですね。
では、また。